1924年創業、世界初のダイナミックヘッドホンを開発したドイツの老舗「beyerdynamic(ベイヤーダイナミック)」。
プロのスタジオ現場で「業界標準」として愛用されるなど、「原音忠実」な音作りで絶対的な信頼を得ているブランドです。
そんなbeyerdynamicが、ワイヤレス市場に投入したのが、今回レビューする「AVENTHO 100」です。
本機は、同社のワイヤレスラインナップで「エントリーモデル」とされつつも、価格帯はミドルハイクラス。
これは、エントリーであっても音質に一切妥協しないという、同社の「専門性」の表れにほかなりません。
「AVENTHO 100」が市場でユニークな存在となっている最大の理由は、その「オンイヤー型」というフォームファクタです。
ANCワイヤレスヘッドホン市場が「オーバーイヤー型」主流の中、本機はあえて耳の上に乗せるオンイヤー型を採用。
これにより、beyerdynamicの音質を追求しつつ、「コンパクトさ」「軽量性」「携帯性」を重視するユーザー層に、明確な選択肢を提示しています。
この記事では、プロが信頼するbeyerdynamicのDNAが、このコンパクトな一台にどう凝縮されているのか、私の「経験」に基づき徹底解剖します。
この記事でわかること(AVENTHO 100の注目ポイント):
- beyerdynamicの「本気」: エントリーモデルでありながら、45mmの大口径ドライバーとaptX Lossless対応という音質への妥協のなさ。
- オンイヤー型の実力: 遮音性、装着感はオーバーイヤー型と比べてどうなのか?
- 音質の詳細: プロが愛用する「モニターサウンド」の系譜を感じられるのか?
- 機能と携帯性: ANC、マルチポイント、USBオーディオ接続、そして圧倒的な軽さ。
音質に妥協はしたくない、でも日々の通勤や移動で身軽に持ち運びたい——。
そんな要求を持つオーディオファンにとって、「AVENTHO 100」は救世主となり得るのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
beyerdynamic 「AVENTHO 100」の製品概要

まずは、「AVENTHO 100」がどのような製品なのか、その基本情報と立ち位置を、客観的なスペックや上位モデルとの比較を交えながら整理します。
「ドイツ御三家」beyerdynamicのブランドと製品の立ち位置
前述の通り、beyerdynamicは「ドイツ御三家」の一角(※)として、長きにわたり音響業界をリードしてきました。
(※一般的に、SENNHEISER(ゼンハイザー)、ULTRASONE(ウルトラゾーン)、そしてbeyerdynamicを指します。)
彼らの製品は、音楽を「楽しむ」ためのリスニング用と、音楽を「作る」ためのプロフェッショナル用(モニター用)に大別されますが、その境界線は時に曖昧です。
なぜなら、すべての製品の根底に「原音忠実」という哲学が流れているからです。
「AVENTHO 100」は、コンシューマー(一般消費者)向けのワイヤレス製品ですが、その音作りの根幹には、プロの現場で培われた技術と耳が活かされています。
本機は、手軽に持ち運べるオンイヤー型でありながら、「beyerdynamicの音」を体験できる、いわば「持ち運べるスタジオモニター」の入り口として位置づけられています。
オンイヤー型ワイヤレスとしての主な仕様とスペック
「AVENTHO 100」の基本性能を一覧表にまとめます。
このスペック表を見るだけでも、本機が「ただのエントリーモデル」ではないことがお分かりいただけるでしょう。
beyerdynamic AVENTHO 100 主要スペック一覧
| カテゴリ | 仕様詳細 | 備考(特筆すべき点) |
|---|---|---|
| 基本形式 | 密閉型 オンイヤー | 耳の上に乗せるタイプ。 |
| ドライバー | 45mm ダイナミックドライバー | オンイヤー型としては異例の大口径。 |
| Bluetooth | Version 5.4 | 最新規格に対応。 |
| 対応コーデック | SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless | CD品質(16bit/44.1kHz)のロスレス伝送に対応。 |
| 再生時間 | 最大60時間(ANCオフ時) | 業界トップクラスのスタミナ。 |
| 最大40時間(ANCオン時) | ANCオンでも十分すぎる駆動時間。 | |
| 急速充電 | 15分の充電で15時間再生 | 非常に強力な急速充電性能。 |
| ノイズキャンセル | アダプティブ ANC | 周囲の騒音に適応するANCを搭載。 |
| 外音取り込み | 搭載(トランスペアレンシーモード) | ボタン一つで周囲の音を確認可能。 |
| 接続機能 | マルチポイント接続 | 2台のデバイスと同時接続可能。 |
| USBオーディオ接続 | USB-CケーブルでPC/スマホとデジタル接続可能。 | |
| 有線接続 | 3.5mm ステレオミニジャック | 電源オフ時でもパッシブヘッドホンとして使用可。 |
| 重量 | 約226.5g | ANC搭載機としては驚異的な軽さ。 |
| 操作 | 物理ボタン | 右ハウジング下部に集約。 |
| その他 | 専用アプリ「MIY」対応(予定) | (本レビュー時点では詳細機能は順次対応) |
注目すべきは、やはり「aptX Lossless」への対応と、「45mmドライバー」の搭載、そして「約226.5g」という軽さです。
aptX Losslessは、対応するスマートフォン(Snapdragon 8 Gen 1以降を搭載する多くのAndroid端末など)との組み合わせで、Bluetooth経由でありながらCD音質を非圧縮で伝送できる技術です。
ワイヤレスの利便性と有線の高音質を両立させる、まさに音質派待望のコーデックです。
また、オーバーイヤー型でも40mm径が一般的な中、それより小型のオンイヤー型に45mmもの大口径ドライバーを搭載している点に、beyerdynamicの音質への執念が感じられます。
上位モデル「AVENTHO 300」との主な違い
beyerdynamicには、「AVENTHO 100」の兄貴分とも言える「AVENTHO 300」(および、その兄弟機「AMIRON 300」)というワイヤレスヘッドホンが存在します。
購入を検討する上で、これらの違いは明確にしておく必要があります。
AVENTHO 100 vs AVENTHO 300 主な違い比較表
| 比較項目 | AVENTHO 100 (本機) | AVENTHO 300 (上位モデル) | 考察・ポイント |
|---|---|---|---|
| 装着スタイル | オンイヤー型 | オーバーイヤー型 | **最大の相違点。**携帯性か、快適性か。 |
| ドライバー | 45mm ダイナミック | STELLAR.45ドライバー | 300はより上位のドライバーを搭載。 |
| 重量 | 約226.5g | 約319g | **約90g以上軽い。**この差は非常に大きい。 |
| 操作方法 | 物理ボタン | タッチセンサー | 100は確実性、300は直感性。 |
| 自動装着検出 | 非搭載 | 搭載 | 300は外すと自動で音楽が停止する。 |
| 急速充電 | 15分で15時間 | 10分で5時間 | 100の急速充電は非常に優秀。 |
| 価格帯 | 約3万6千円台 | 約6万8千円台 | 価格差は約2倍。 |
この比較表から、「AVENTHO 100」は単なる廉価版ではなく、明確な思想(=ポータビリティの追求)を持って設計されたモデルであることがわかります。
「AVENTHO 300」が「自宅やオフィスでじっくりと最高のワイヤレスサウンドを」というコンセプトなのに対し、「AVENTHO 100」は「beyerdynamicのサウンドを、どこへでもアクティブに持ち運ぶ」というコンセプトです。
自動装着検出などの快適機能(QOL機能)を省略する一方で、軽量化を徹底し、急速充電性能を高めている点に、その設計思想が色濃く反映されています。
beyerdynamic 「AVENTHO 100」の外観デザインと携帯性

ここからは、実際に製品を手に取って感じた「モノ」としての質感、デザイン、そして携帯性について、私の経験に基づきレビューします。
パッケージ内容と付属のソフトケース
パッケージは、ブランドカラーであるオレンジを差し色にした、シンプルかつ洗練されたデザインです。
過剰な装飾はなく、製品写真とロゴが中心の、いかにもドイツの工業製品といった趣があります。
開封してまず目に入るのは、専用のキャリングケースです。
付属品一覧:
- AVENTHO 100 本体
- 専用ソフトキャリーバッグ
- USB-C to USB-A ケーブル(充電およびデータ転送用)
- 3.5mm オーディオケーブル (両端ミニプラグ)
- クイックスタートガイド、保証書
一点、注意すべきは、付属するのが「ソフトケース」であることです。
上位モデルの多くがハードケースを採用しているのに対し、本機は布製(とはいえ、しっかりとした厚みとクッション性はある)のソフトケースです。
これは一見コストダウンのように思えますが、私は「携帯性」を突き詰めた結果の選択だと解釈しました。
ハードケースは保護性能こそ高いものの、それ自体が大きく、かさばります。
一方、このソフトケースは、ヘッドホン本体を折りたたんで収納すると、驚くほどコンパクトにまとまります。
バッグの中で余計なスペースを取らず、本体の軽さをスポイルしない。
このソフトケースの採用もまた、「AVENTHO 100」の「ポータビリティ重視」という思想の表れだと感じました。
コンパクトで堅実な本体デザインと質感
今回レビューしたのは「ブラウン」モデルです。
他にも「ブラック」「クリーム」がラインナップされていますが、このブラウンが非常に良い質感でした。
ハウジング(耳当ての外側)は、マット(艶消し)仕上げ。
しっとりとした手触りで、指紋が全く目立ちません。プラスチック素材ではありますが、安っぽさは皆無。
中央から少しずれた位置に「AVENTHO 100」のロゴが控えめにプリントされており、非常に上品です。
ヘッドバンドからハウジングを保持するアーム部分、そしてヘッドバンドの長さを調節するスライダー部分は、細身ながらも堅牢な金属製です。
この金属パーツが、全体の質感を格段に引き上げています。
スライダーの動きは無段階式で、ぬるぬるっと滑らかに動き、任意の位置でピタッと止まります。
この精度の高い動作感は、まさにドイツのクラフトマンシップを感じる部分です。
イヤーパッドとヘッドバンドのクッションは、非常に柔らかい合成皮革で、肌触りは良好です。
全体として、デザインは「華美」ではなく「堅実」。流行に左右されない、タイムレスなバウハウス的デザインとも言えるかもしれません。
Tシャツとジーンズのようなラフな格好から、ジャケットスタイルまで、どんな服装にも自然に馴染む懐の深さがあります。
折りたたみ機構と物理ボタンの操作性
携帯性について、もう少し深掘りします。
本機は、ハウジングを内側に折りたたむ「フォールディング機構」を備えています。
これにより、前述のソフトケースに収めると、ほぼ手のひら大(成人男性)のサイズにまで小さくなります。
約226.5gという重量も相まって、500mlのペットボトル飲料よりも軽く、小さいのです。
これは、日常的にバッグに入れて持ち運ぶ上で、圧倒的なアドバンテージとなります。
操作性についても、私は高く評価しています。
「AVENTHO 100」は、すべての操作を右ハウジングの下部に集約された「物理ボタン」で行います。
物理ボタンのメリット:
- 誤操作がない: 近年の流行であるタッチセンサー式は、意図せず触れてしまったり、雨や汗で濡れると誤作動したりすることがあります。物理ボタンなら、カチッという確実なクリック感があるため、操作ミスがありません。
- 手探りでの操作が容易: 各ボタンの形状や配置が工夫されているため、慣れればヘッドホンを装着したまま、手探りだけで再生/停止、音量調整、曲送り/戻し、ANCの切り替えが可能です。
特に冬場、手袋をしている状態でも確実な操作ができるのは、物理ボタンならではの強みです。
ANC/外音取り込みの切り替えボタンが、電源ボタン(短押しで機能)と兼用になっている点も合理的だと感じました。
beyerdynamic 「AVENTHO 100」の装着感と機能性の詳細チェック

「AVENTHO 100」の最大の関心事、それは「オンイヤー型の装着感」と「ANC性能」でしょう。
私の実体験を基に、詳しくレビューします。
オンイヤー型特有の装着感と側圧について
結論から言うと、「AVENTHO 100」の装着感は「短時間集中型」。万人に快適とは言えないが、明確なメリットがある、というものです。
装着感の実際:
- 側圧(頭を挟む力): やや強めです。
- イヤーパッド: 非常に柔らかく、耳への当たりは優しい。
- 重量: 非常に軽い。頭頂部への負担は皆無。
オーバーイヤー型が「耳の周り」をクッションで囲むのに対し、オンイヤー型は「耳(耳介)そのもの」をクッションで上から押さえつけます。
なぜ側圧が強めなのか?
これは設計上の意図があり、主に2つの理由が考えられます。
- 音響的理由:
オンイヤー型は、耳とドライバーの間に隙間ができると、そこから低音が逃げてしまい、スカスカな音になりがちです。
それを防ぎ、ドライバー本来の豊かな低音を鼓膜に届けるため、一定の側圧で耳に密着させる必要があります。 - 遮音性の確保:
隙間をなくすことで、ANCの土台となる「パッシブノイズキャンセリング(物理的な遮音性)」を高めることができます。
この設計思想の結果、「AVENTHO 100」の装着感は、1〜2時間程度の使用(例えば、毎日の通勤・通学、カフェでの短時間作業)では、その軽さも相まって非常に快適です。
ズレにくく、安定しています。
ただし、弱点もあります。
- 長時間の使用:
私の場合、2時間を超えてくると、押さえつけられている耳介がじんわりと痛くなってきました。 - メガネユーザー:
これが最大の難関かもしれません。
メガネの「つる」の上からパッドで押さえつける形になるため、つるが耳の後ろに食い込み、痛みが出やすいです。
私は装着時に少しメガネを浮かせ、ヘッドホンのパッドが直接耳に当たるように位置を調整することで、ある程度回避できましたが、オーバーイヤー型のような「無」の快適さはありません。
この装着感は、本機を選ぶ上での最大のトレードオフです。
「長時間の快適性」を何より重視する人(例:1日中ヘッドホンをつけていたい人)には、正直なところお勧めしにくいです。
しかし、「持ち運びの良さ」と「1〜2時間単位での使用」を繰り返す人にとっては、この上なく合理的な装着感とも言えます。
アクティブノイズキャンセリング(ANC)と外音取り込み機能
「AVENTHO 100」のANC性能は、「オンイヤー型としては驚くほど強力」と評価できます。
前述の強めの側圧と高い密閉性(パッシブ遮音性)が非常に良く効いています。
その上でANCをオンにすると、特に「ゴー」「ボー」といった低周波数の定常騒音が劇的に低減されます。
シーン別ANC効果:
- 電車内:
電車の走行音(ゴーーー)は、ほぼ無音に近いレベルまで抑えられます。音楽のボリュームを上げなくても、細部まで聴き取れます。ただし、「ガタンゴトン」という衝撃音や、車内アナウンス(中高域)はパッシブ遮音性がメインで対応する形で、ある程度聞こえます。 - カフェ:
空調の「ブーン」という音や、遠くの話し声は綺麗に消えます。近くの人の明確な会話や、食器の「カチャカチャ」という高い音は、音楽を流していれば気にならないレベルまで低減されます。 - 路上:
車の走行音はかなり小さくなりますが、安全上、ある程度聞こえるようにチューニングされている印象も受けます。
総合的に、オーバーイヤー型のトップティア(例:Sony 1000XシリーズやBose QCシリーズ)の「完全な静寂」と比べると一歩譲りますが、オンイヤー型であることや、その軽さを考えれば、十分すぎる実用的なANC性能を持っていると言えます。
外音取り込み(トランスペアレンシーモード)
電源ボタンの短押しで切り替えられる外音取り込み機能は、標準的な性能です。
マイクで拾った音だと分かる、やや人工的な音質ですが、音楽を停止すればレジでの会話や駅のアナウンスを聞き取るのに全く問題はありません。
一点だけ惜しいのは、ANCオン → ANCオフ → 外音取り込み → ANCオン、というローテーションであること。
ANCと外音取り込みをワンボタンで直接切り替えたい、というのが正直な感想です。
マルチポイント接続と通話品質
現代のワーカーにとって必須とも言えるマルチポイント機能。
「AVENTHO 100」は、もちろん対応しています。
マルチポイントの挙動:
私の環境(iPhone 15 ProとMacBook Air)でテストしたところ、非常にスムーズに動作しました。
- iPhoneとMacBookにそれぞれペアリングします。
- ヘッドホンの電源を入れると、即座に両方に自動接続されます。
- MacBookで音楽を聴いている最中に、iPhoneに電話がかかってくると、シームレスに音声がiPhoneに切り替わり、通話が可能です。
- 通話が終われば、自動でMacBookの音楽再生(一時停止されていた)に戻れます。
挙動は、後から再生信号を送った方に切り替わるのではなく、先に再生を開始したデバイスが優先される「先勝ち」仕様に近い安定したものでした。
意図しないデバイスの音(通知音など)で音楽が途切れることがなく、ストレスフリーです。
通話品質(マイク性能)
通話品質は「良好」です。静かな室内であれば、相手には非常にクリアな音声が届きます。
騒いでも、声が埋もれて聞き取れない、ということはありませんでした。
Web会議やビジネス通話にも、問題なく使用できるレベルです。
私の体験談:beyerdynamic 「AVENTHO 100」の音質と使用感レビュー

さて、いよいよ本機の核心である「音質」についての詳細なレビューです。
経験に基づき、私が「AVENTHO 100」で音楽を聴いて感じたことを、できるだけ具体的に記述します。
(試聴環境:iPhone 15 Pro (AAC), Android端末 (aptX Adaptive), PC (USBオーディオ接続))
beyerdynamicらしい原音に忠実なモニターサウンド
「AVENTHO 100」のサウンドを一言で表すなら、「フラットバランスを基調とした、高解像度なモニターサウンド」です。
これは、昨今のワイヤレスヘッドホンに多い、低音と高音を強調した派手な「ドンシャリ」サウンドとは一線を画します。
初めて聴いた瞬間、「ああ、これがbeyerdynamicの音だ」と納得させられる、極めて真面目で誠実な音作りです。
- 音場(音の広がり):
オンイヤー型ということもあり、広大なホールで聴くようなスケール感はありません。どちらかというと、良質なスタジオのモニタールームで、ニアフィールドスピーカー(近距離用スピーカー)で聴いているような、密度が高く、定位のハッキリした音場です。 - 解像度:
抜群に高いです。それぞれの楽器が、どの位置で、どのように鳴っているのかが手に取るようにわかります。音が「団子」になることが一切ありません。
高解像度で質感の高い低音域の表現力
本機のサウンドレビューで、私が最も特筆したいのが「低音域」の質です。
一般的なワイヤレスヘッドホンの低音:
「ドンドン」「ブンブン」と鳴る、「量」や「迫力」を重視したものが多い。
AVENTHO 100の低音:
「ドッ」「グッ」と沈み込む、「質」と「スピード感」を重視した低音です。
45mmの大口径ドライバーが、オンイヤー型特有のタイトな音響空間で駆動することで、極めて反応が良く、輪郭のハッキリした低音を生み出しています。
ジャンル別・音質レビュー:
- ロック / ポップス (例: Official髭男dism, King Gnu):
ボーカルがセンターにピシッと定位し、決して他の楽器に埋もれません。特筆すべきは、ベースラインの追いやさ。複雑なフレーズを弾くベースの「一音一音」が、ドラムのキックと混ざることなく、明確に聞き取れます。ギターリフのキレも鋭く、音楽全体の「グルーヴ」をダイレクトに感じられます。 - ジャズ (例: ビル・エヴァンス, マイルス・デイヴィス):
このヘッドホンの真価が発揮されるジャンルの一つです。ウッドベースの弦が指板に当たる「カチッ」という音、シンバルレガートの「チキチー」という金属的な響き、ピアノのハンマーが弦を叩く瞬間の「アタック音」。そういった**微細なディテール(空気感)**の再現性が尋常ではありません。目を閉じれば、演奏者の息遣いまで伝わってくるようです。 - クラシック (例: オーケストラ):
広大な音場表現は得意ではありませんが、室内楽や協奏曲では、各楽器の音色(ねいろ)を生々しく描き分けます。ヴァイオリンの弦が擦れる質感、管楽器の艶やかさなど、誇張のないリアルな音を楽しめます。 - EDM / ヒップホップ:
「量感」で圧倒するタイプの低音ではないため、クラブで聴くような「音の洪水」を求める人には物足りないかもしれません。しかし、シンセベースの「うねり」や、キックの「深さ」は正確に再現します。あくまで「楽曲制作者が作った音」を忠実に鳴らす、というスタンスです。
ANCオン/オフ時で異なるサウンドの印象
多くのANC搭載機がそうであるように、「AVENTHO 100」もANCのオン/オフで音質がわずかに変化します。
- ANCオフ時:
これが本機の「素」の音であり、最も優秀なサウンドです。S/N比(信号と雑音の比率)が最も高く、雑味のない、非常にクリアで見通しの良い音。音場もわずかに広く感じられます。自宅などでじっくり音楽を聴く際は、オフを推奨します。 - ANCオン時:
オフ時に比べ、低音域がわずかにブースト(増強)されます。これは、ANCが低周波音を打ち消す処理の副産物か、あるいは意図的なチューニング(騒音下でも低音を聴き取りやすくするため)だと思われます。 この変化は「劣化」というほどのものではなく、むしろ屋外の騒音下では、この方が音楽の迫力や土台がしっかりと感じられ、バランスが良く聴こえることもしばしばでした。
この音質変化は非常に小さく、両者の違いを神経質に気にする必要はありません。
シーンに応じて積極的にANCを活用すべきです。
USBオーディオ接続による高音質化の検証
「AVENTHO 100」の隠れた(しかし強力な)機能が、USBオーディオ接続です。
付属のUSB-CケーブルでPC(MacBook)やスマートフォン(iPhone 15 Pro)に接続すると、ヘッドホンが自動的に「USB-DAC」として認識されます。
Bluetooth接続との違い:
- バッテリー消費なし: ヘッドホン本体のバッテリーを消費しません(むしろ充電される)。
- デジタル伝送: Bluetoothのような圧縮(aptX Adaptive)やロスレス(aptX Lossless)を経由せず、音源データをデジタルのままヘッドホンに送り込み、ヘッドホン内蔵のDAC(デジタル→アナログ変換器)で処理します。
音質の変化:
Bluetooth (aptX Adaptive) 接続でも十分に高音質ですが、USBオーディオ接続に切り替えた瞬間、音の「厚み」と「鮮度」が一段階向上するのがハッキリと分かりました。
例えるなら、Bluetoothが「上質なミネラルウォーター」だとしたら、USBオーディオ接続は「源泉から汲み上げたばかりの湧き水」のような、生々しさとエネルギー感が加わります。
特に、ハイレゾ音源(24bit/96kHzなど)を再生した際は、音の粒子がさらに細かくなり、空間の余韻がより豊かに感じられました。
この機能のおかげで、「AVENTHO 100」は「外では高音質なワイヤレスヘッドホン」「自宅やオフィスでは、高音質なPC用有線ヘッドホン」という、一台二役の使い方が可能になります。
これは極めて大きなメリットです。
通勤・屋外使用における遮音性とポータビリティ
私の主な使用シーンである「片道1時間の電車通勤」において、「AVENTHO 100」は最高の相棒の一つとなりました。
- 携帯性:
バッグからサッと取り出し、使い終わればサッと折りたたんで仕舞える。この軽快さが、重くかさばるオーバーイヤー型にはない最大の魅力です。 - 遮音性:
前述の通り、オンイヤー型とは思えないANCとパッシブ遮音性で、通勤のストレスである騒音から解放され、音楽に没入できます。 - 音漏れ:
オンイヤー型は音漏れを心配されがちですが、本機は密閉性が高いため、常識的な音量(iPhoneのボリュームで60%程度)であれば、満員電車でも周囲に迷惑をかけることはないレベルでした。
体験談の総括
「AVENTHO 100」を数週間にわたり、あらゆるシーンで使い倒してみて、私はこのヘッドホンを「音質に妥協しない、現実主義者のためのポータブル・モニター」と結論付けました。
beyerdynamicの真髄である「原音忠実」なサウンド、特にその緻密で上質な低音の表現力は、ワイヤレスかつオンイヤー型であることを忘れさせるほどの圧倒的なクオリティです。
一方で、オンイヤー型特有の強めの側圧は、高い遮音性と引き換えに、長時間の快適性をある程度犠牲にしている明確な「トレードオフ」が存在します。
しかし、そのおかげでANCの効果も高まり、軽量コンパクトな設計と相まって、移動中や騒がしい場所での「良質な音の体験」を力強くサポートしてくれます。
USBオーディオ接続という「音質をさらに追求できる奥の手」が残されている点も、オーディオファンとしては高く評価できるポイントです。
利便性だけでなく、音のクオリティにも妥協したくない、そんなアクティブな音楽リスナーにとって、「AVENTHO 100」は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
beyerdynamic 「AVENTHO 100」に関するQ&A
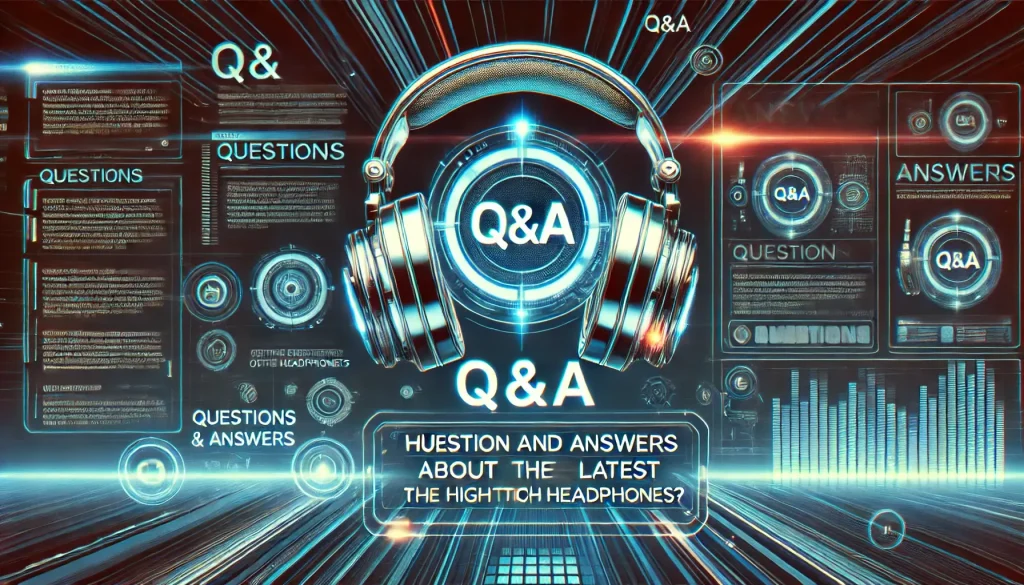
beyerdynamic 「AVENTHO 100」に関して、よく聞かれそうな質問とその回答をまとめました。
メガネユーザーでも快適に使えますか?
正直、あまり快適とは言えません。オンイヤー型は耳を直接圧迫するため、メガネのつるが耳の後ろに食い込み、痛くなりやすいです。短時間なら大丈夫な場合もありますが、購入前に試着をおすすめします。
オンイヤー型ですが、音漏れはしますか?
常識的な音量であれば、あまり心配いりません。密閉性が高い設計なので、電車やカフェで音楽を聴いても、周囲に迷惑をかけることは少ないでしょう。
上位モデルのAVENTHO 300と、どちらを選ぶべきですか?
使う場所と時間で選ぶのがおすすめです。
- AVENTHO 100 (本機): 「持ち運び」重視。軽くてコンパクトなので、通勤・通学など外出先での使用がメインの方に。
- AVENTHO 300 (上位機): 「快適さ」重視。耳を覆うので、家やオフィスで長時間ゆったり使いたい方に。
3.5mmの有線接続(アナログ)時の音質はどうですか?
BluetoothやUSB接続と比べると、音質は劣ります。全体的に音がこもったように聞こえがちです。あくまでバッテリーが切れた時などの「緊急用」と考えるのが良いでしょう。
ゲームや動画視聴での音ズレ(遅延)は気になりますか?
YouTubeなどの動画視聴では、音ズレはほとんど気になりません。 音ゲーやFPSなどタイミングがシビアなゲームでは、少し遅れを感じる可能性があります。PCゲームなら、遅延がゼロになるUSB接続をおすすめします。
aptX Losslessに対応しているメリットは何ですか?
対応するAndroidスマートフォンなどと接続した場合、Bluetooth経由でもCD音質(16bit/44.1kHz)の音楽データを劣化させずに(ロスレスで)伝送できます。従来のSBCやAACといったコーデックよりも、高音質なワイヤレス再生が可能です。
充電しながらBluetoothで音楽を聴けますか?
いいえ、できません。USB-Cケーブルを接続して充電中、またはUSBオーディオ接続中は、Bluetooth機能がオフになる仕様です。
USBオーディオ接続は、PC以外(スマートフォン)でも使えますか?
はい、使えます。USB-C端子を持つスマートフォン(iPhone 15シリーズや多くのAndroid端末)やiPadなどにケーブルで接続すれば、高音質なデジタル再生が可能です。
オンイヤー型は、夏場に蒸れやすいですか?
耳全体を覆うオーバーイヤー型に比べると、耳との接触面積が小さいため、蒸れは「比較的マシ」です。とはいえ、イヤーパッドが耳に密着する構造なので、気温が高い日に汗をかけば、蒸れを感じることはあります。
SONYやBoseの定番モデルと比べて、強みは何ですか?
「AVENTHO 100」の最大の強みは、「音質(原音忠実なモニターサウンド)」と「携帯性(軽さ・コンパクトさ)」の両立です。 他社の多機能モデルはANC性能や快適機能で優れることが多いですが、本機は「beyerdynamicの本格的な音を、どこへでも身軽に持ち運びたい」というニーズに特化しています。
防水性能はありますか? 雨の日や運動中に使えますか?
いいえ、公式スペックに防水性能の記載はありません。そのため、雨天時の使用や、汗をかくようなスポーツでの使用は推奨されません。あくまで日常の移動や室内での使用を想定したモデルです。
まとめ:「AVENTHO 100」レビューの総合評価とおすすめできる人

最後に、beyerdynamic 「AVENTHO 100」のレビューを総括し、どのような人に適したヘッドホンなのか、公平な視点で分析します。
総評:音質に妥協しないモバイルユーザーへの選択肢
「AVENTHO 100」は、「オンイヤー型」「ワイヤレス」「エントリーモデル」というカテゴリーでありながら、音質に関しては一切の妥協を感じさせない、beyerdynamicの哲学が詰まった希有な製品です。
優れた携帯性(軽さ・コンパクトさ)と、同ブランドが誇る原音忠実なモニターサウンドを、極めて高いレベルで両立させています。
ただし、それは「長時間の快適性」や「多機能性(自動装着検出など)」といった要素を、ある程度トレードオフにした上で成り立っています。
このヘッドホンの評価は、ユーザーが何を最優先するかによって、大きく分かれるでしょう。
「AVENTHO 100」の明確な強み(メリット)
本機を「買うべき理由」となる、明確な強みを箇条書きでまとめます。
- 圧倒的な音質: beyerdynamic伝統の「原音忠実」な高解像度サウンド。特に低音の「質」と「スピード感」は同価格帯のワイヤレス機でトップクラス。
- 究極の携帯性: 約226.5gという圧倒的な軽さと、コンパクトな折りたたみ機構。日常的に持ち運ぶ際のストレスが皆無。
- オンイヤー型最強クラスの遮音性: 強めの側圧による高いパッシブ遮音性と、実用十分なANC性能の組み合わせが強力。
- 多彩な接続性: aptX Lossless対応に加え、音質がさらに向上する「USBオーディオ接続」という奥の手を持つ。
- 驚異的なバッテリー性能: 最大60時間(ANCオフ)のスタミナと、「15分充電で15時間再生」という強力すぎる急速充電。
購入前に知っておくべき注意点(デメリット)
一方で、購入前に必ず許容できるか確認すべき「弱点」や「注意点」です。
- 装着感(側圧)の問題: オンイヤー型特有の強めの側圧。長時間の使用(目安:2時間以上)で耳が痛くなる可能性がある。
- メガネユーザーへの非推奨: メガネのつるの上から圧迫するため、痛みを誘発しやすい。メガネユーザーは必須で試着を推奨。
- 快適機能(QOL)の省略: 上位モデルにある「自動装着検出(外すと停止)」機能が非搭載。
- 操作系の細かな不満: ANC/外音取り込みの切り替え時に、必ず「ANCオフ」を経由する仕様。
このヘッドホンを推奨するユーザー像
以上の強みと弱点を踏まえ、「AVENTHO 100」を心からお勧めできるのは、以下のような方です。
- 音質最優先のモバイルリスナー: 「音質は絶対に妥協したくないが、重いオーバーイヤー型を通勤で持ち運ぶのは億劫だ」と感じている人。
- 原音忠実なサウンドが好きな人: 低音ドンドン、高音シャリシャリの派手な音に飽きた、アーティストの意図を聴き取りたい人。
- ロック・ジャズ・アコースティック系の音楽ファン: 楽器の生々しさ、ベースラインの解像度、ボーカルの質感を重視する人。
- PC作業と併用したい人: 外ではワイヤレス、オフィスや自宅ではPCとUSB接続して高音質で作業したい人。
他の選択肢を検討すべきユーザー像
逆に、以下のような方には、「AVENTHO 100」は適していない可能性が高く、他の選択肢(例:AVENTHO 300や他社のオーバーイヤー型)を検討すべきです。
- 長時間の快適性を最優先する人: 「1日中ヘッドホンをつけていたい」「装着したまま寝てしまう」という使い方をする人。
- メガネを常にかけている人: (試着なしでの購入は、特に危険です)
- 「完全な静寂」を求める人: ANC性能を最重要視し、業界最高レベルの静寂性を求める人。
- 自動装着検出などの便利機能が必須な人: ヘッドホンを外すたびに、いちいち再生を停止するのが面倒だと感じる人。
beyerdynamic 「AVENTHO 100」レビューの総括
「AVENTHO 100」は、約3万6千円台という価格で、beyerdynamicの本格的なサウンドシグネチャと、考え抜かれたポータビリティを両立させた、非常にコストパフォーマンスの高いモデルです。
弱点である「側圧の強さ」は、裏を返けば「高い遮音性と携帯性」というメリットの源泉でもあります。
このヘッドホンが「自分にとって最高の相棒」になるか「残念な買い物」になるかは、あなたがヘッドホンに求める優先順位、特に「音質・携帯性」と「長時間の快適性」のどちらを天秤にかけるかにかかっています。
私の個人的な結論としては、「1〜2時間の通勤・移動」という用途に限定すれば、これほど音質と携帯性を高いレベルで満たしてくれる選択肢は他にない、と感じています。
購入を検討している方は、本記事のレビューを参考にしつつ、ぜひ一度店頭で「できれば30分」試着してみてください。
その装着感が許容できるならば、「AVENTHO 100」は、あなたのかけがえのない「音楽を持ち運ぶ」ための最高のツールとなることをお約束します。




