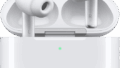有線イヤホン市場は、完全ワイヤレスイヤホンが普及した今でも根強い人気を誇っています。
特に「1万円前後」の価格帯は、初めて高音質を求める人から、既に複数のイヤホンを所有する愛好家まで幅広い層に支持されている領域です。
その中で注目を集めているのが、オーディオメーカー Shanling(シャンリン) が手掛ける最新モデル 「SONO S」。
Shanlingはデジタルオーディオプレーヤーの分野で長年の実績を積み上げてきたメーカーで、音づくりへの信頼感があります。
今回登場した「SONO S」は、かつて高い評価を受けた「SONO」の系譜を継ぐ後継機として設計され、進化した仕様と現代的なデザインで注目を集めています。
特徴的なのは、2基のダイナミックドライバーと1基のバランスド・アーマチュアドライバーを組み合わせたハイブリッド構成。
加えて、チタンコーティング振動板や交換式フィルター、メタルシェルなど、この価格帯では珍しい仕様を惜しみなく搭載しています。
この記事では、この「SONO S」の仕様やサウンド傾向、実際の使い勝手をレビューしていきます。
初めて本格的な有線イヤホンを検討している人にも、イヤホン収集が趣味の人にも役立つ内容を目指しています。
SONOシリーズの位置づけと進化

初代「SONO」は「複数ドライバーを活かした厚みのあるサウンド」が高く評価されました。
「SONO S」はその系譜を継ぎつつ、より統一感のある音作りへと進化しています。
ドライバー構成の刷新
- 初代:異なる振動板素材のDDを組み合わせ
- SONO S:両方ともチタンコート振動板に統一し、音色の一体感を重視
技術的特徴
- 同軸デュアルDD+専用クロスオーバーで帯域のつながりを改善
- カスタムBAにより高域の抜けや透明感を補強
- HCCAWボイスコイル/N50マグネティック回路/PUサスペンションで駆動効率やレスポンスを強化
ユーザー体験の拡張
- 交換式フィルター(ニュートラル/アンビエンス)で音傾向を調整可能
- 小型メタルシェルと重心設計により、重量を感じにくい装着感
価格帯と競合モデルとの比較
1〜1.5万円前後のイヤホンは「単一DD」や「1DD+1BA」が主流で、樹脂シェルが多いのが現状です。
対して「SONO S」は、メタルシェル+2DD+BA+交換式フィルターという“盛り込み型”仕様で差別化しています。
| 項目 | 一般的な製品傾向 | SONO Sの特徴 |
|---|---|---|
| ドライバー構成 | 単一DD or 1DD+1BA | 2DD(9.2/6.8mm)+BA |
| ドライバー素材 | 標準コート | チタンコートDD×2 |
| ドライバー配置 | 通常配置 | 同軸配置+クロスオーバー |
| シェル素材 | 樹脂・軽金属 | 亜鉛合金メタル(手磨き仕上げ) |
| 音傾向調整 | 固定が多い | 交換式フィルター2種 |
| ケーブル | OFC中心 | 銀メッキOFC(32芯×4) |
| 認証 | 非対応もあり | Hi-Res Audio認証 |
メリット
- 価格を超えた豪華仕様(フィルター、メタルシェル、銀メッキケーブル)
- 音の一体感+高域の見通しを両立
- 小型・耐久性・質感を兼備
注意点
- 付属は3.5mmのみ → バランス接続は別途ケーブル購入が必要
- 有線専用のため、スマホ直挿しには端子やアダプタの確認が必要
どんなユーザー層に向いているか
- 初めてのハイブリッドIEMを試したい人
→ 低域の厚みと高域の透明感をバランスよく体験可能 - 音のカスタマイズを楽しみたい人
→ フィルター交換でニュートラル/低域寄りを簡単に切り替え - 質感や耐久性を重視する人
→ メタルシェルによる高級感と堅牢性 - 普段使いを重視する人
→ 16Ω・103dBでスマホやDAPでも駆動しやすい - 3.5mm中心の環境を持つ人
→ 手持ち機材とそのまま組み合わせやすい
Shanling 「SONO S」の仕様と特徴

Shanling 「SONO S」は、2DD+1BAのハイブリッド構成を採用した1万円台前半の有線イヤホンです。
単なる“エントリー機”に留まらず、チタンコート振動板や交換式フィルター、メタルシェル、リケーブル対応など、上位機に迫る要素を盛り込んでいます。
ここでは、その仕様と特徴を3つの観点から整理します。
ハイブリッド構成と駆動設計
「SONO S」の心臓部は、9.2mmと6.8mmのチタンコートDD+カスタムBAによる3基のドライバー。
同軸配置と専用クロスオーバーにより、自然で滑らかな帯域のつながりを実現しています。
- 同軸デュアルDD構造:時間整合が良く、低域から中域まで一体感のある響き
- 役割分担
- 9.2mm DD → 沈み込む低音と量感
- 6.8mm DD → 中域の明瞭さと厚み
- カスタムBA → 高域の伸びと透明感を補強
- 駆動技術:HCCAWボイスコイル、N50デュアルマグネティック回路、PUサスペンションを採用し、歪みを抑えながら瞬発力のあるサウンドを実現
低域の迫力と高域の抜けを両立し、エントリー機ながらバランスの良い音作りを狙っています。
チタンコート振動板と交換式フィルター
「SONO S」では、両方のDDにチタンコート振動板を採用。
素材を揃えることで音色の統一感が生まれ、滑らかな帯域表現につながります。
さらに、好みに合わせて音傾向を変えられる交換式フィルターも魅力です。
| フィルター | 音の傾向 | おすすめ用途 |
|---|---|---|
| ニュートラル(黒リング) | バランス重視。クリアで素直な音質 | 幅広いジャンルに対応、基準チューニング |
| アンビエンス(赤リング) | 低域が厚くなり音場拡大。迫力重視 | ポップス、EDM、映画やゲーム |
1台で“ニュートラル”と“低域寄り”を切り替えられるため、シーンに応じた音作りが可能です。
デザイン・装着感・拡張性
外観は、亜鉛合金のメタルシェルを高精度成型し、手作業で磨き上げたラグジュアリーな仕上がり。
重量は片側8.3gですが、重心設計により装着時に重さを感じにくい設計になっています。
- コンパクト設計:同軸レイアウトでハウジングを小型化、耳に自然に収まる
- リケーブル対応:0.78mm 2pin採用、4.4mmバランスケーブルへの換装も可能
- 付属ケーブル:4×32芯の銀メッキOFCケーブル(3.5mmプラグ)。ノイズを抑え、手軽に高音質を楽しめる
- 駆動性:16Ω/103dBでスマホや小型DAPでも鳴らしやすい
- Hi-Res Audio認証:20Hz〜40kHzの広帯域再生に対応
主要スペックまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ドライバー構成 | 9.2mm DD(Tiコート)×1、6.8mm DD(Tiコート)×1、カスタムBA×1 |
| 周波数特性 | 20Hz〜40,000Hz(Hi-Res対応) |
| インピーダンス/感度 | 16Ω/103±3dB |
| コネクタ | 0.78mm 2pin |
| 付属ケーブル | 銀メッキOFC 4×32芯(3.5mm、約1.3m) |
| 重量 | 約8.3g(片側) |
| 付属品 | フィルター2種、イヤピース2種、キャリングケース など |
「SONO S」は、「豪華なハイブリッド構成」×「音傾向を変えられる遊び心」×「質感の高いメタルシェル」を備えた、価格以上の満足度を狙えるモデルです。
特に“音の統一感”と“フィルターでの変化”を楽しめるのは大きな特徴といえるでしょう。
Shanling 「SONO S」のサウンドレビュー

Shanling 「SONO S」は、低域の厚みと高域の透明感を両立させたサウンドが特徴です。
2基のダイナミックドライバーを同一素材のチタンコート振動板で揃えたことで、帯域間のつながりが非常に自然。
さらに高域用のカスタムBAが加わることで、暗く沈み込みやすい低域に“抜け”を与えています。
帯域ごとの音質傾向
低域
- 量感はやや多めで、深く沈み込むタイプ
- 弾力感がありタイトに収束、残響は短め
- EDMやロックのキックやベースに力強さを付与
中域
- ボーカルが前に出て、明瞭で聴き取りやすい
- 厚みを持ちながら、曇りのないクリアさ
- ギターやピアノの響きに芯があり、合奏でも埋もれにくい
高域
- シンバルや弦楽器の倍音が伸びやか
- 粒立ちが細かく、金属的に尖りすぎない
- 高域の存在感は十分だが刺さりにくいチューニング
音場と定位
- 横幅は中〜広め、前後の重なりも把握しやすい
- ボーカルがセンターに安定して定位し、楽器の分離も良好
音質傾向まとめ
| 項目 | 評価(5段階) |
|---|---|
| 低域の迫力と沈み込み | 4.5 |
| 中域の明瞭さと厚み | 4.5 |
| 高域の伸びと透明感 | 4.0 |
| 音場の広さ | 4.0 |
| 解像感(価格比) | 4.0 |
| ダイナミクス(表現力) | 4.5 |
交換式フィルターの効果
「SONO S」には、ニュートラル(黒)/アンビエンス(赤)の2種類のフィルターが付属。
音傾向の切り替えは明確で、シーンやジャンルに応じて使い分けられます。
| フィルター | 音の変化 | 合うジャンル/シーン |
|---|---|---|
| ニュートラル(黒) | 全帯域がバランス良く、クリアで見通しの良い音 | 幅広いジャンル、長時間リスニング |
| アンビエンス(赤) | 低域が厚みを増し、音場も広がる。迫力重視 | ポップス、EDM、映画やライブ音源 |
たとえば普段はニュートラルで“基準の音”を楽しみ、EDMや映画鑑賞の際はアンビエンスで没入感を高める、といった使い分けが可能です。
同価格帯イヤホンとの比較
1〜1.5万円帯のイヤホンは、単一DDや樹脂シェルが多く、音傾向も固定的なものが中心です。
「SONO S」はそれに比べ、ハイブリッド構成・金属シェル・交換式フィルターという贅沢な仕様でアドバンテージを持っています。
強み
- 2DDを同素材で統一 → 音色に一体感
- 高域用BAで透明感を補強 → 暗くならず見通し良好
- 金属シェルで振動を抑制し、装着感も安定
- フィルター交換で2種類の音を楽しめる → 幅広いジャンル対応
注意点
- 超上位機ほどの微細描写や分離感は望めない
- 標準ケーブルは3.5mmのみ → バランス接続はリケーブル必須
- 低域がしっかりしているため、完全フラットを好む人にはやや濃い印象
Shanling 「SONO S」は、迫力ある低域と抜けの良い高域を両立させた、バランスの取れたサウンドが持ち味です。
加えてフィルター交換で音傾向を変えられるため、日常的に幅広い音楽ジャンルを楽しみたいユーザーに適した1本といえます。
Shanling 「SONO S」を使用した私の体験談・レビュー

Shanling 「SONO S」を数日間使い込んでみて感じたのは、「厚みと見通しのバランスが良く、使い勝手に優れたイヤホン」だということです。
特に、フィルター交換やイヤピースの選び方でキャラクターが変わり、シーンに合わせた楽しみ方ができるのが魅力でした。
装着感とビルドクオリティ
装着感は期待以上で、金属シェルなのに軽快に感じられました。
- 重さ:片側8.3gと金属製にしては軽量
- 設計:耳の内側に重心が寄るため、装着時に重さを感じにくい
- 仕上げ:フェイス部分は立体的な陰影があり、見た目の高級感は価格以上
遮音性も十分で、通勤・作業中に使っても周囲の雑音をしっかりカットできました。
音質の印象(ニュートラルフィルター基準)
低域
- 量感はやや多めだが、膨らまずにタイト
- キックやベースが沈み込み、迫力とスピード感を両立
中域
- ボーカルが半歩前に出る定位
- 厚みがありつつも濁らず、ギターやピアノも明快
高域
- 伸びやかで透明感があり、シンバルの粒立ちも自然
- 刺さる帯域は抑えられており、長時間聴いても疲れにくい
音場・定位
- 横幅は標準〜やや広め
- 前後の重なりがわかりやすく、ボーカルと伴奏の位置関係がつかみやすい
ジャンルごとの相性
| ジャンル | 印象 | おすすめ設定 |
|---|---|---|
| ポップス | ボーカルが際立ち、伴奏と分離が良い | 黒フィルター+標準イヤピ |
| ロック | キックが力強く、ギターに芯がある | 黒または赤フィルター |
| EDM/ヒップホップ | 低域の沈み込みが心地よく、ノリ良し | 赤フィルター+厚肉イヤピ |
| ジャズ | 金物の粒立ちが繊細、ウッドベースもふくよか | 黒フィルター+フォーム |
| クラシック | セクションの重なりが見えやすく、弦が伸びやか | 黒フィルター+密閉性重視イヤピ |
フィルター切り替えの実用性
- ニュートラル(黒):全体の見通しが良く、万能。レビュー基準にも最適。
- アンビエンス(赤):低域が強まり、音場が広がる。EDMや映画視聴で迫力が増す。
イヤピースとの組み合わせでさらに調整できるため、一本で二役以上の楽しみ方ができます。
良かった点と気になった点
良かった点
- 低域の迫力と中域の明瞭さを両立
- フィルター交換で音のキャラクターが明確に変わる
- 金属シェルの質感と装着の安定感
- 駆動しやすく、スマホ直でも十分楽しめる
気になった点
- 上位機ほどの微細な描写や分離感は望めない
- 付属は3.5mmケーブルのみ → バランス派は別途リケーブル必須
- 低域が豊かな設計のため、完全フラット志向のリスナーには濃く感じるかも
体験談まとめ
実際にShanling 「SONO S」を使い込んでみて強く感じたのは、この価格帯では珍しいほど「音の厚みと見通しの良さが絶妙に両立している」ということでした。
低域は沈み込みが深く、しっかりとした土台を作りながらも過剰に膨らむことはなく、リズムのスピード感をきちんと維持しています。
その上に中域が自然に乗るため、ボーカルは常に一歩前に出て聴こえ、歌声が楽曲全体の中心に据えられている印象を受けました。
高域はカスタムBAの存在が効いており、金物や弦楽器の倍音がきらびやかに響きつつも耳に刺さらないバランスが保たれていて、長時間聴いても疲れにくい点は好感が持てます。
装着感についても、金属シェルでありながら重さを意識させない作り込みが光ります。
重心が耳の内側に収まるように設計されているため、長時間のリスニングでも負担が少なく、遮音性も良好でした。
さらに、フィルターを切り替えることで音のキャラクターが明確に変わるのも大きな魅力で、ニュートラルではクリアでバランスの取れた音を楽しめ、アンビエンスでは低域の迫力と音場の広がりを味わえるなど、一本のイヤホンで二つの表情を持つことができるのは非常に楽しい体験でした。
全体を通して、「SONO S」は「エントリークラスでありながら遊び心と完成度を兼ね備えたイヤホン」と言えるでしょう。
音のまとまりやデザインの質感に加え、駆動のしやすさやリケーブル対応といった拡張性も備えており、日常使いのメイン機としても、コレクションの一本としても十分に満足できる内容でした。
Shanling 「SONO S」に関するQ&A

Shanling 「SONO S」に関して、よく聞かれそうな質問とその回答をまとめました。
「SONO S」はどんなイヤホンですか?
Shanlingが手掛ける2DD+1BAのハイブリッド構成イヤホンです。低域の迫力と高域の透明感を両立し、交換式フィルターで音傾向を切り替えられるのが特徴です。
初代「SONO」との違いは何ですか?
初代は2つのDDで異なる振動板素材を採用していましたが、「SONO S」では両方をチタンコート振動板に統一。音色の一体感と帯域の滑らかなつながりが向上しています。
どんな音の特徴がありますか?
- 低域:沈み込みが深く、タイトで迫力がある
- 中域:ボーカルが前に出てクリア
- 高域:BAによる抜け感と透明感で伸びやか
→ 総じて「厚みと見通しのバランス」が魅力です。
フィルターはどう使い分けるのがおすすめですか?
- ニュートラル(黒):バランス重視。ジャンルを問わず聴きやすい
- アンビエンス(赤):低域が増して音場が広がり、EDMや映画向き
フィルター交換は簡単にできますか?
ノズル先端のフィルターを付け替える方式で、工具不要。数十秒で交換できるため、気分や曲のジャンルごとに手軽に切り替えられます。
装着感はどうですか?
片側約8.3gと金属製にしては軽量。重心が耳の内側に寄るため、長時間でも違和感が少なく快適に使えます。
駆動はスマホでも可能ですか?
インピーダンス16Ω/感度103dBと鳴らしやすいため、スマホ直挿しでも十分楽しめます。USB-DACやDAPに繋げば低域の階調や音場の奥行きがさらに向上します。
ケーブルの交換はできますか?
はい、0.78mm 2pin規格を採用しており、4.4mmバランス接続などへのリケーブルが可能です。標準では3.5mm銀メッキOFCケーブルが付属しています。
他社製の同価格帯と比べて強みは?
一般的に1万円台は単一DDや樹脂シェルが多い中、SONO Sは金属シェル・2DD+BA・交換式フィルター・銀メッキOFCケーブル・Hi-Res認証と、仕様が充実している点が大きな優位性です。
遮音性はどの程度ありますか?
金属シェルによる密閉感とカナル型デザインにより、通勤電車やカフェなどでも環境音をある程度カットできます。完全遮音ではありませんが、一般的なカナル型以上の遮音性があります。
バランス接続にすると音は変わりますか?
4.4mmバランスケーブルに換装すると、左右の分離感が向上し、低域の制動もタイトになります。純正付属は3.5mmのみですが、リケーブルで音の伸び代を楽しめます。
耐久性はどうですか?
金属シェルは強度が高く、樹脂製に比べて傷や歪みに強いです。リケーブル対応なのでケーブル断線時も本体を長く使えます。
Shanling 「SONO S」レビューのまとめ
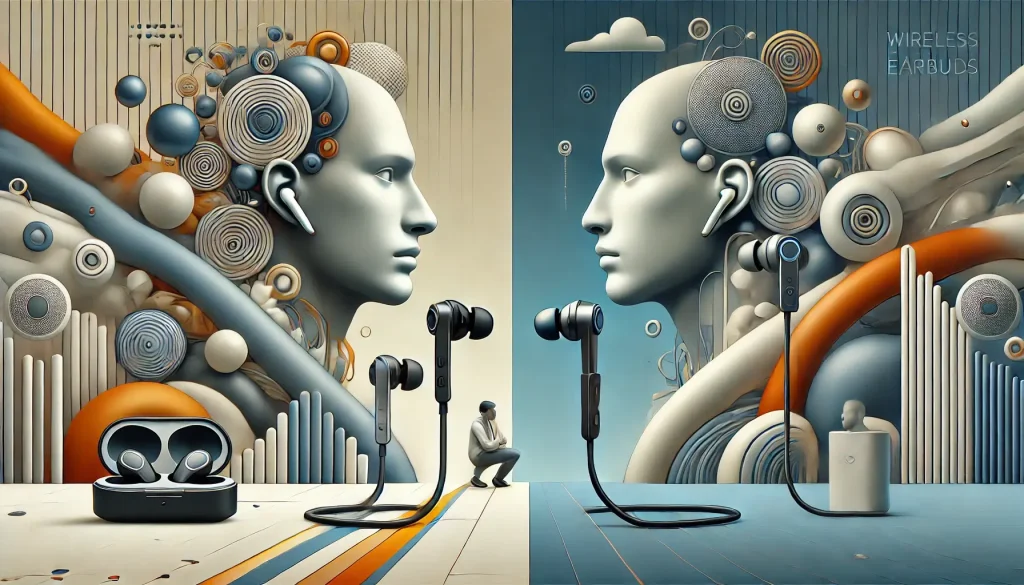
Shanling 「SONO S」は、1万円台前半とは思えない完成度で、厚みのある低域/クリアで前に出る中域/伸びやかな高域を、同一素材(チタンコート)の2DD+高域用BAで自然に繋いだ“統一感のあるハイブリッド”。
小型メタルシェルの質感・装着安定性、16Ω/103dBの鳴らしやすさ、0.78mm 2pinの拡張性、さらに交換式フィルターで味付けを変えられる自由度まで備え、日常使いのメイン機にも最初の本格IEMにも勧めやすい一本です。
総合ハイライト
- 音の要点:低域は沈み込みが深くタイト/ボーカルは半歩前で明瞭/高域は粒立ちよく刺さりにくい
- 音色の一体感:両DDをチタンコートで統一+同軸配置&専用クロスオーバーで帯域が滑らかに接続
- 使い勝手:片側8.3gの小型メタルで装着安定、通勤〜作業までストレス少なめ
- 駆動性と伸び代:スマホ直でもOK。USB-DAC/DAP/リケーブルで階調・静けさが伸びる
- 可変チューニング:ニュートラル(黒)/アンビエンス(赤)の2種フィルターで“基準音”と“迫力重視”を即切替
長所と留意点
長所
- 価格以上のハードウェア:2DD+1BA/メタルシェル/銀メッキOFC(4×32芯)/Hi-Res認証
- 低域の土台×高域の見通しでジャンル横断の聴きやすさ
- フィルター&イヤピースで明確に味変できる楽しさ
留意点
- 付属は3.5mm SEのみ(4.4mm等は別途ケーブルが前提)
- 超上位機のような顕微鏡的分離・微小音の極限描写は狙っていない
- 設計上低域の存在感が持ち味 → 完全フラット志向にはやや濃いと感じる可能性
シーン別おすすめ設定
| シーン/狙い | 推奨フィルター | イヤピース傾向 | ねらいどころ |
|---|---|---|---|
| 作業BGM/ジャンル横断 | ニュートラル(黒) | 標準シリコン | バランスと見通しを最優先 |
| EDM・映画・ライブで没入 | アンビエンス(赤) | 厚肉シリコン | 低域厚み+音場感アップ |
| 長時間リスニング | 黒 | フォーム系 | 角を丸めて疲労感を軽減 |
| 情報量を一段底上げ | どちらでも | 好みでOK | 小型USB-DAC/DAP追加で階調・背景の静けさが向上 |
| さらに分離感と締まり | どちらでも | – | 4.4mmバランス化(別売ケーブル)で左右分離と低域制動を強化 |
こんな人にフィット
- 初めてのハイブリッドIEMで「厚みと透明感の両立」を体験したい
- 曲や気分で音傾向を切り替えて楽しみたい(フィルター/イヤピ調整が好き)
- 質感・耐久性の高いメタルシェルを長く使いたい
- 3.5mm中心の環境で手堅くまとめ、後からDACやリケーブルで拡張したい
購入前チェックリスト
- 3.5mmで使う? → 付属ケーブルだけで即運用可
- バランス接続派? → 2pin 4.4mmケーブルを別途用意
- 使い分け重視? → 黒=基準/赤=没入を想定
- 機材アップの計画は? → USB-DAC or DAPで階調・音場の底上げ余地あり
Shanling 「SONO S」レビューの総括
Shanling 「SONO S」は、エントリークラスに位置づけられる価格帯でありながら、確かな設計思想と丁寧な仕上げが感じられる一本でした。
2基のチタンコートDDとカスタムBAによるサウンドは、低域の迫力と中高域の透明感を絶妙に両立させ、音の一体感を重視した完成度の高いチューニングに仕上がっています。
金属シェルならではの高級感と軽快な装着性、交換式フィルターによる音傾向の切り替え、さらにはリケーブル対応とHi-Res認証まで備え、長く楽しめるポテンシャルを秘めています。
もちろん、超上位機のような緻密な分離や描写力には及ばない部分もありますが、その分、気軽に扱える使いやすさや駆動のしやすさが魅力として際立っています。
総じて、初めて本格的なハイブリッドIEMを試す人にも、手堅いサブ機を求める愛好家にも勧められる、価格を超えた価値のある製品だといえるでしょう。
音楽を日常に寄り添わせたいすべての人に、Shanling 「SONO S」は新しいリスニング体験をもたらしてくれるはずです。