「1万円台で、本格的な“開放型”ヘッドホンが欲しい」
「密閉型の圧迫感が苦手で、スピーカーで聴くような自然な音場で音楽に浸りたい」
「でも、エントリークラスの開放型は、音がスカスカだったり、安っぽかったりしないか不安だ」
もしあなたがこのような悩みをお持ちなら、この記事はまさにあなたのために書かれています。
今回、私が2週間にわたり(合計40時間以上)徹底的に聴き込み、その驚くべきポテンシャルに惚れ込んだのが、Kiwi Earsの開放型ヘッドホン「Altruva(アルトルーヴァ)」です。
なぜ今、この1万円台前半のヘッドホンに注目すべきなのか?
結論から言えば、「Altruva」は「1万円台の価格で、5万円クラスの音場の広さと解像度を“体験できる”可能性を秘めたヘッドホン」だからです。
ただし、このヘッドホンには、その真価を発揮させるために絶対に欠かせない「条件」があります。
この記事は、単なるスペック紹介や当たり障りのない音質評価ではありません。
オーディオ専門家として、そして一人の音楽ファンとしての具体的な使用体験に基づき、このヘッドホンの「本当の実力」と「正しい鳴らし方」を徹底的に解明します。
この記事を読み終える頃には、Kiwi Ears 「Altruva」があなたのオーディオライフを劇的に変える一台になるか、それとも宝の持ち腐れになってしまうか、その全てが明確になっているはずです。
Kiwi Ears 「Altruva」とは? – 製品概要とビルドクオリティ

まずは、Kiwi Ears 「Altruva」がどのような製品なのか、その背景と実機の品質(ビルドクオリティ)から詳しく見ていきましょう。
IEMで名を馳せた「Kiwi Ears」の哲学と「Altruva」の立ち位置
Kiwi Earsは、2021年頃に登場した比較的新しい中国のオーディオブランドです。
彼らはもともとIEM(インイヤーモニター:イヤモニ)の分野で、その価格からは信じられないほどの高解像度と緻密なチューニングで世界中のマニアを驚かせ、一気に人気ブランドの仲間入りを果たしました。
代表作である「Orchestra」や「Quartet」などは、音楽制作用のモニターとしても使えるほどの原音忠実性とバランス感覚を、驚異的なコストパフォーマンスで実現しています。
そんな彼らがIEMで培った「原音に忠実で、色付けの少ないモニターサウンド」という哲学を、そのままヘッドホンに持ち込んだのが、今回紹介する「Altruva」を含むヘッドホンラインナップです。
Kiwi Earsのヘッドホンラインナップは、現在(2025年時点)主に以下のようになっています。
| モデル名 | ドライバー構成 | 価格帯(目安) | 特徴・立ち位置 |
|---|---|---|---|
| Division | 40mm DD | 約8,000円 | 手軽に楽しめるエントリーモデル |
| Ellipse | 50mm DD | 約10,000円 | 開放型の入門機。明るく抜けのある音 |
| Altruva | 50mm DD | 約12,000円 | 本記事の主役。Ellipseを明確にブラッシュアップ。広い音場と高い解像度。 |
| Atheia | 50mm DD + 14.5mm平面磁気 | 約50,000円 | ハイエンド志向のハイブリッド構成 |
※DD = ダイナミックドライバー
この表から分かる通り、「Altruva」は同社の開放型ラインナップにおける「中核モデル」であり、入門機「Ellipse」の上位互換として、ブランドの哲学を最も強く体現する戦略的な機種と言えます。
基本スペックと技術的特徴(50mm DDドライバーのポテンシャル)
「Altruva」の性能を理解するために、まずは基本スペックを見てみましょう。
| 項目 | 内容 | 筆者コメント |
|---|---|---|
| 形式 | 開放型(オープンバック) | 音が自然に抜け、広い音場を実現。音漏れはあり。 |
| ドライバー | 50mmダイナミックドライバー | 大口径ならではの豊かで歪みの少ない中低域に期待。 |
| 振動板 | PU+PEK複合振動板 | 応答性が良く、クリアで解像度の高い音質に寄与。 |
| インピーダンス | 32Ω | 一般的な数値。スマホでも鳴らせるが…。 |
| 感度 | 98dB ± 3dB | **【最重要】**この数値が「やや低い」のが最大の鍵。 |
| 接続端子 | 3.5mm(6.35mm変換アダプター付属) | 標準的な規格。 |
| ケーブル | 着脱式 3m 布巻きケーブル | デスク周りでの使用を想定した長さ。リケーブル可能。 |
| イヤーパッド | ヴィーガンレザー / ベロアの2種類同梱 | 音質と装着感を好みで選べる、非常に太っ腹な仕様。 |
| 重量 | 約370g(ケーブル含まず) | 中量級。装着感のセクションで詳しく後述。 |
| 価格帯 | 約10,000〜12,000円前後 | このスペックと付属品で、驚異的な価格。 |
ここで専門的な視点から最も注目すべきは、「感度 98dB」という数値です。
インピーダンス(抵抗)は32Ωと普通ですが、感度(音の鳴らしやすさ)が100dBをわずかに下回っています。
これは、「スマートフォン直挿しでは、十分な音量と“音の力強さ”が得られない可能性がある」ことを示唆しています。
この「鳴らしにくさ」こそが、「Altruva」のポテンシャルを引き出す「アンプ」の必要性に直結します(詳しくは後述)。
実機開封と1万円台を超えたビルドクオリティ検証
まず驚かされるのは、1万円台とは思えない立派な化粧箱と、そのビルドクオリティ(製品の質感・作り込み)です。
- ハウジング(本体外側):
ハウジングは金属製のグリル(網)と、Blackwood(黒檀)風のシックな樹脂パーツで構成されています。
この金属グリルは非常に剛性が高く、指で押してもたわむことはありません。
視覚的にも「音が抜けていきそう」な開放感を演出しています。 - ヘッドバンドとヨーク(アーム部分):
ヘッドバンドのフレームと、ハウジングを支えるヨーク部分はすべて金属製です。
プラスチックを多用する同価格帯の他機種と比べ、明らかに高い剛性と高級感を備えています。
日常的にラフに着脱しても、まず壊れることはないだろうという安心感があります。 - 付属品(イヤーパッド):
前述の通り、肌触りの良い「ベロア素材」と、密閉感を高める「ヴィーガンレザー素材」の2種類が標準で付属します。
これは通常、別売りで数千円してもおかしくないもので、この時点でコストパフォーマンスの高さを感じさせます。
正直なところ、外観と触感だけで言えば、2〜3万円クラスの製品と遜色ありません。
「安かろう悪かろう」という先入観は、この製品に限っては完全に捨て去るべきです。
Kiwi EarsがIEMで培った品質管理のノウハウが、ヘッドホンにも活かされている証拠でしょう。
Kiwi Ears 「Altruva」の装着感と開放型ヘッドホンとしての特性

どれだけ音が良くても、装着感が悪ければ長時間の音楽鑑賞には耐えられません。
その点、「Altruva」は非常に優れた回答を用意していました。
最高のフィット感:「自己調整式バンド」と「選べる2種のパッド」
「Altruva」の装着感を「最高」たらしめている要因は、以下の2つです。
1. 自己調整式ヘッドバンド(フリーアジャストヘッドバンド)
「Altruva」は、一般的なヘッドホンのように「カチカチ」とスライダーを伸縮させて長さを調整する必要がありません。
頭に被るだけで、内側の合皮製バンドが頭の形に合わせて自動的に最適な長さに伸び、ぴったりとフィットします。
これは高級ヘッドホン(例:AKG K701シリーズなど)に採用される機構で、装着のたびに微調整するストレスから解放されます。
2. 2種類のイヤーパッドによる「選択肢」
付属する2種類のイヤーパッドは、装着感と音質に明確な違いをもたらします。
| パッド種類 | 装着感(肌触り) | 密着度 | 蒸れにくさ | 音質の傾向 |
|---|---|---|---|---|
| ベロア | 非常に柔らかく、優しい | やや低い | ◎ (非常に快適) | 音の抜けが良く、音場が最も広く感じられる。高音が爽やか。 |
| ヴィーガンレザー | しっとりと肌に吸い付く | 高い | △ (やや蒸れる) | 密閉感が上がり、低音の量感と厚みが増す。没入感重視。 |
この「選べる」という体験は非常に重要です。
夏場は通気性の良いベロアで快適に、冬場や映画鑑賞で迫力を出したい時はレザーで、といった使い分けが可能です。
長時間・メガネ使用時の快適性(側圧と重量バランス)
私(筆者)はメガネを常にかけており、ヘッドホンのレビューにおいて「メガネとの相性」は死活問題です。
- 重量(約370g)について:
数値だけ見ると「中量級」で、やや重く感じるかもしれません。
しかし、前述の自己調整式バンドが頭頂部への圧力を非常にうまく分散させるため、数字ほどの重さを全く感じさせません。 - 側圧(耳を挟む力)について:
側圧は「やや強め」に分類されます。これによりヘッドホンがズレにくく、安定した装着感が得られます。 - 【Experience】メガネユーザーとしての2週間レポート:
- ベロアパッドの場合:
非常に快適でした。パッドが柔らかいためメガネのフレームを優しく包み込み、2〜3時間の連続使用でも全く痛くなりませんでした。 - レザーパッドの場合:
密着度が高い分、1時間を超えたあたりからメガネのツルが当たる部分(耳の後ろ)に少し圧迫感を感じました。
- ベロアパッドの場合:
結論として、メガネユーザーの方には、デフォルトで「ベロアパッド」の使用を強く推奨します。
この組み合わせなら、長時間のデスクワークや音楽鑑賞でも、疲れ知らずの快適性を約束できます。
開放型の宿命:「音漏れ」と「遮音性」のリアルな実態
ここで、開放型ヘッドホンを選ぶ上で最も重要な遮音性や音漏れに関わる情報をお伝えします。
1. 遮音性(外の音をどれだけ防げるか)
- 結論:皆無です。
- 音楽を再生していなければ、装着していない時とほぼ同じように周囲の音が聞こえます。エアコンの音、キーボードのタイプ音、家族の話し声、すべて聞こえます。
- これは欠点ではなく、「周囲の気配を感じながら音楽にも集中できる」という開放型のメリットでもあります。
2. 音漏れ(中の音がどれだけ外に漏れるか)
- 結論:盛大に漏れます。
- ハウジングのグリル部分から、音がそのまま外に拡散します。イメージとしては「耳元に小さなスピーカーを2つ置いている」状態に近いです。
- 筆者の実環境テスト:
- 静かな自室(深夜): 小音量(iPhoneの30%程度)でも、3m離れた場所にいる家族から「何か音楽が鳴っている」と指摘されました。
- 一般的なリビング(日中、テレビあり): 中程度の音量(iPhoneの50%〜60%)で、隣の席(約1m)に座ると「シャカシャカ」という音が明確に聞こえます。
【警告】このヘッドホンは、以下の環境では絶対に使用できません。
- 電車、バスなどの公共交通機関
- 図書館、カフェ
- 家族が寝ている静かな寝室(よほど小音量でない限り)
「Altruva」は、「音漏れを気にしなくて良い、静かな自室」で、その真価を発揮する専用機であると断言します。
この点を理解せずに購入すると、必ず後悔します。
音質徹底検証 – 「Altruva」は「アンプで化ける」は本当か?

お待たせしました。
本レビューの核心、音質についての専門的な検証です。
結論から言えば、「Altruvaはアンプで化ける」というのは、100%真実です。
「Altruva」がアンプを要求する技術的理由(インピーダンス32Ω/感度98dBの罠)
「なぜアンプが必要なのか?」その答えは、前述したスペックにあります。
- インピーダンス 32Ω: これは問題ありません。一般的な数値です。
- 感度 98dB: これが問題です。
オーディオ機器の「感度」とは、「1mWの電力を入力した時に、どれだけ大きな音(dB)を出せるか」という効率を示す数値です。
一般的なイヤホンやポータブルヘッドホンは、感度が105dB〜110dB程度あります。
感度が「98dB」のAltruvaは、感度「108dB」のイヤホンと比較した場合、同じ音量を出すために「10倍」の電力(パワー)を必要とする計算になります。
(※dBは対数なので、10dBの差は電力比で10倍)
スマートフォンのイヤホンジャックや、安価なドングルDAC(変換アダプタ)は、この「10倍の電力」を安定して供給するようには設計されていません。
【アンプなし(スマホ直挿し)で起こること】
- そもそも最大音量が小さく、満足するまで音量を上げられない。
- (最重要)たとえ音量が取れても、音の「瞬発力」や「制動力」が足りなくなる。
- 低音がボワボワと膨らみ、締まりがなくなる。
- 音場が狭く、全ての音が頭の中心で平面的に鳴る(いわゆる“頭内定位”)。
- 高音が伸びきらず、全体的に霞がかかったような音になる。
「Altruva」は、「十分なパワー(駆動力)を持つアンプによって、50mmの大口径ドライバーをしっかりと“制動”してあげる」ことが、良い音で鳴らすための絶対条件なのです。
スマホ直挿し vs 据え置きアンプで音はどう“開花”するか
この「音の変化」を、私の実体験に基づき、具体的に描写します。
[検証1] スマートフォン(iPhone 15 + 純正変換アダプタ)直挿し
- 音量: まず、音量がギリギリです。普段の音量(50%)では小さすぎ、80%〜90%まで上げて、ようやく「聴こえる」レベル。
- 音質: 正直に言って、「1万円の価値はない」と感じました。
- 全体的に音が薄っぺらい。
- 低音は「ドン」ではなく「ポン…」という感じで、アタック感が皆無。
- ボーカルは遠く、霞がかかっている。
- 音場は狭く、開放型ヘッドホンを聴いているという感動が全くない。
- 評価:この状態では、5000円の密閉型ヘッドホンにすら負けています。
[検証2] 1万円クラスのドングルDAC(例:iBasso DC04PROなど)
- 音量: 余裕で取れるようになります。iPhoneの40%〜50%で十分な音量です。
- 音質: 劇的に変化します。ここで初めて「Altruva」の「片鱗」が見えました。
- 低音に「芯」が入り、「ドン」というアタック感が出てきます。
- ボーカルを覆っていた霞が晴れ、クリアに聴こえるようになります。
- 音場が左右に「スッ」と広がるのが明確にわかります。
- 評価:これなら「1万円のヘッドホン」として納得できる音質です。
[検証3] 5万円クラスの据え置きアンプ(例:FiiO K7など)
- 音量: もはや余裕。
- 音質: “開花”します。これが「Altruva」の真の姿でした。
- 全ての音が「覚醒」します。
- 低音は「ドン」から「ドッ!」という、深く、速く、タイトな「制動された音」に変わります。
- ボーカルはクリアなだけでなく、「息遣い」や「口元の動き」まで見えるような生々しさを獲得します。
- 音場が爆発的に広がります。左右だけでなく、前後・上下にも空間が広がり、音が頭の外、まるでスピーカーから鳴っているかのように聴こえます。
- 評価:これが1万円台のヘッドホンから出る音とは、にわかには信じられません。5万円クラスのヘッドホン(例:HIFIMAN Sundara)に迫る音場感と解像度です。
音域別サウンド分析:刺さらない「空気感」とタイトで速い「低音」
上記の[検証3](据え置きアンプ)環境で聴いた、「Altruva」の真の音質を分析します。(※ベロアパッド使用時)
全体の傾向:
ややクール(寒色系)で、フラット〜弱ドンシャリ。
色付けが少なく、音源の良し悪しを暴き出すモニターライクな側面を持ちながら、開放型らしい「空気感」と「響きの美しさ」を両立しています。
高音域:刺さらず、どこまでも伸びる「空気感」
- 「Altruva」の最大のハイライトです。
- シンバルやハイハットの音は、刺さる(耳に痛い)帯域を絶妙にコントロールしつつ、天井を突き抜けるかのようにスッと伸びて消えていきます。
- この「消え際の余韻」が、音楽全体の“空気感”や“臨場感”を生み出しています。
- 密閉型では決して味わえない、透明感と抜けの良さです。
中音域:ボーカルの「距離感」と「息遣い」のリアルな表現
- ボーカルは近すぎず、遠すぎず、ステージの中央やや奥に自然に定位します。
- (アンプで駆動すると)声の芯がしっかりとし、特に女性ボーカルの息遣いや、ハモリの分離感が非常に明瞭になります。
- アコースティックギターやピアノの弦の響きも、非常にリアル。変な色付けがないため、アーティストが意図した音色をそのまま楽しめます。
低音域:量感より「スピード」と「解像度」
- 開放型ヘッドホンの特徴として、低音の「量感」(ズンズン響く迫力)は控えめです。
- その代わり、「Altruva」の低音は「圧倒的にタイト(締まっている)」です。
- ベースラインは一音一音がボヤけず、輪郭を持って聴き取れます。ドラムのキックも「ボワッ」ではなく「ダッ!」と速く、キレが良い。
- このスピード感のある低音が、音楽全体の見通しを良くし、中高域のクリアさを際立たせています。重低音の迫力を求める人には向きませんが、「質の高い低音」を求める人には最適です。
Kiwi Ears 「Altruva」を使用した私の体験談・レビュー

ここでは、私の体験に基づき、私が「Altruva」を2週間使い込んだ、極めて個人的かつリアルな感想をお伝えします。
私が「ベロアパッド」と「据え置きアンプ」を標準環境にした理由
試行錯誤の末、私の「Altruva」の標準セッティングは「ベロアパッド + 据え置きアンプ(FiiO K7)」に固定されました。
- なぜレザーパッドではないのか?
レザーパッドは確かに低音の迫力と没入感を増してくれます。
しかし、それは「Altruva」が持つ最大の魅力である「音場の広さ」と「高音の抜け」をわずかにスポイルしてしまうと感じました。
低音の迫力が欲しければ、最初から密閉型ヘッドホンを選びます。
私が「Altruva」に求めたのは、開放型でしか味わえない「空気感」でした。 - なぜドングルDACではないのか?
1万円クラスのドングルDACでも、音質が「合格点」に達することは確認できました。
しかし、据え置きアンプに繋ぎ変えた瞬間の「世界が一気に広がる感覚」を知ってしまった後では、もうドングルDACには戻れませんでした。
「Altruva」は、アンプの性能が上がれば上がるほど、正直に音質を向上させてくる「ポテンシャルの塊」です。
ベストマッチだった音楽ジャンル(J-POP女性ボーカル、ライブ音源)
このセッティングで聴いて「鳥肌が立った」ジャンルは以下の通りです。
- 女性ボーカル(J-POP、アニソン):
- 例:Aimer, milet, YOASOBIなど
- 透明感のあるボーカルと、Altruvaの高音の抜けの良さが完璧にマッチします。息遣いが耳元でリアルに感じられ、ハモリのパートが綺麗に分離して空間に溶けていく様は圧巻です。
- ライブ音源(ロック、アコースティック問わず):
- これが最強でした。
- 「Altruva」の広大な音場が、コンサートホールの「広さ」や「天井の高さ」まで再現するかのようです。
- 観客の歓声や拍手が、頭の中ではなく、自分の周囲(頭の外)から聞こえてきます。この「定位の良さ」は、まさにライブ音源を聴くためにあると言っても過言ではありません。
- アコースティック、クラシック(小編成):
- ギターの弦を弾く指の動き、ピアノのペダルの踏み込み、ヴァイオリンの弓が擦れる音。そういった「微細な音」を、驚くほど生々しく拾い上げます。
逆に、EDMやヒップホップなど、重低音の「圧」そのものを楽しみたいジャンルには、正直あまり向いていません。
作業用BGMとしての適性(聴き疲れしにくい音)
私はデスクワーク中に音楽を流し続けることが多いのですが、「Altruva」はこの用途にも最適でした。
- 理由1:装着感が快適(ベロアパッド)
自己調整バンドと通気性の良いベロアパッドのおかげで、3時間つけっぱなしでも全く苦になりません。 - 理由2:音が刺さらない
高音は伸びますが、決して耳に痛い「刺さる」音は出さないため、長時間のリスニングでも疲労感が少ないです。 - 理由3:遮音性がない(メリット)
インターホンの音や、家族からの呼びかけを逃すことがありません。作業に集中しつつ、外界との繋がりも保てる絶妙なバランスです。
深夜、小音量でも失われない解像感の魅力
これは意外な発見でした。
通常、ヘッドホンの音量を絞ると、まず低音と高音が聞こえにくくなり、全体的に「ショボい」音になりがちです。
しかし、「Altruva」(とアンプ)の組み合わせは、深夜にしか聴こえないような小音量に絞っても、音の解像度や音場の広がりが、あまり失われないのです。
小音量でも、ボーカルの息遣いや、高音の余韻がしっかりと耳に届きます。
これは、ドライバーの基本的な性能(応答性の良さ)と、アンプの制動力が高いレベルでバランスしている証拠です。
家族が寝静まった深夜、小音量でじっくりと音楽の世界に浸る。
そんな贅沢な時間を、「Altruva」は提供してくれました。
100時間エージング後の音質変化はあったか?
オーディオの世界には「エージング(新品状態から一定時間鳴らし込むことで音質が安定・向上する)」という概念があります。
私はオカルト的なエージングは信じませんが、物理的な可動部(ドライバー)が馴染むことによる「初期変化」はあると考えています。
- 結論:明確な変化がありました。
- 変化点: 新品(箱出し)直後は、高音域にわずかな「硬さ」や「尖り」を感じました。 ↓ 約50時間〜100時間経過後: その高音の硬さが取れ、全体的に音が「なめらか」に、そして「より自然に」伸びるようになりました。中低域との繋がりもスムーズになり、音楽全体の一体感が増した印象です。
これは「劇的な音質向上」というより、「本来の性能が発揮されるようになった」というべき変化です。
「Altruva」を購入した際は、最低でも50時間程度は鳴らし込んでから、その真価を判断することをおすすめします。
体験談の総括:1万円台で「深化」するオーディオ体験
2週間にわたる「Altruva」との時間は、まさに「発見」と「驚き」の連続でした。
最初は「アンプがないと鳴らない」という不便さに戸惑いましたが、環境を整えた瞬間に豹変する音質は、他のエントリークラスのヘッドホンでは決して味わえない「育てる喜び」そのものです。
ベロアパッドによる快適な装着感、作業中も苦にならない抜けの良い音、そして深夜の小音量ですら感じ取れる解像感。
これらすべてが、Kiwi Ears 「Altruva」が単なる「1万円台のヘッドホン」ではなく、オーディオの深い世界への「扉」となる一台であることを証明していました。
派手さはありませんが、聴けば聴くほど、使い込むほどにその良さが「深化」していく。
「Altruva」は、そんな本質的な音楽の楽しみ方を再発見させてくれる、希有なヘッドホンだと結論づけます。
Kiwi Ears 「Altruva」に関するQ&A

Kiwi Ears 「Altruva」に関して、よく聞かれそうな質問とその回答をまとめました。
「Altruva」はどんな人におすすめですか?
開放型ヘッドホンを初めて試してみたい人や、自然な音場と透明感のある音を楽しみたい人に向いています。ボーカル中心の楽曲やアコースティック系、ライブ音源などとの相性が特に良く、音楽を“空気ごと聴く”ような感覚が味わえます。
開放型ヘッドホンって音漏れしますか?
はい、「Altruva」は背面が通気構造になっているため、音漏れはかなりあります。静かな環境や夜間に使用する場合は、周囲に人がいない空間で楽しむのが理想です。逆にその開放構造のおかげで、音の抜けや立体感が格段に向上しています。
スマホ直挿しでも使えますか?
音は出ますが、本領を発揮するにはやや出力不足です。ドングルDACや据え置きのヘッドホンアンプなど、駆動力のある機器を使用することで、音場の広がりと低域の締まりが格段に良くなります。
ベロアとレザーパッドではどちらがおすすめ?
どちらも特徴があり、好みで使い分けるのがおすすめです。ベロアは通気性が高く、音の抜けと開放感を重視したい人向け。ヴィーガンレザーは密閉感が強く、低音の厚みや没入感を楽しみたい人に適しています。
「Ellipse」との違いはありますか?
同じ50mmダイナミックドライバーを採用していますが、「Altruva」の方が解像度が高く、音場の広がりが明確です。より精密な定位と空間表現を求めるなら「Altruva」、鳴らしやすさや扱いやすさを重視するなら「Ellipse」が良い選択でしょう。
ゲームや映画鑑賞にも向いていますか?
はい。開放型ならではの広い音場と定位の良さにより、効果音や環境音の方向感が掴みやすく、臨場感が高まります。ただし、音漏れがあるため共有スペースでの使用は避けた方が無難です。
他ブランドのヘッドホンと比べた特徴は?
同価格帯の密閉型モデルと比べると、「Altruva」は圧倒的に「空気感」と「音場の奥行き」が広いです。一方で、低音の量感は控えめなため、重低音重視のモデルとはキャラクターが異なります。リスニングよりも“音の構造を感じる”聴き方に向いたヘッドホンです。
長時間使用しても疲れませんか?
自己調整式バンドのおかげで装着感が軽く、側圧も適度。パッドを変えることで快適さを調整できるため、4〜5時間の使用でも耳や頭が痛くなることはほとんどありません。
駆動しにくいと聞きましたが、具体的にはどんな環境が理想ですか?
出力の弱いスマホやノートPC直挿しでは音量は取れますが、音の立体感が物足りない場合があります。出力200mW以上のヘッドホンアンプや高性能ドングルDACを使うと、音場が広がり低域も締まってきます。特に据え置き環境では、音の階層表現が明確になり印象が一変します。
Kiwi Ears 「Altruva」レビューのまとめ:総評と購入ガイド
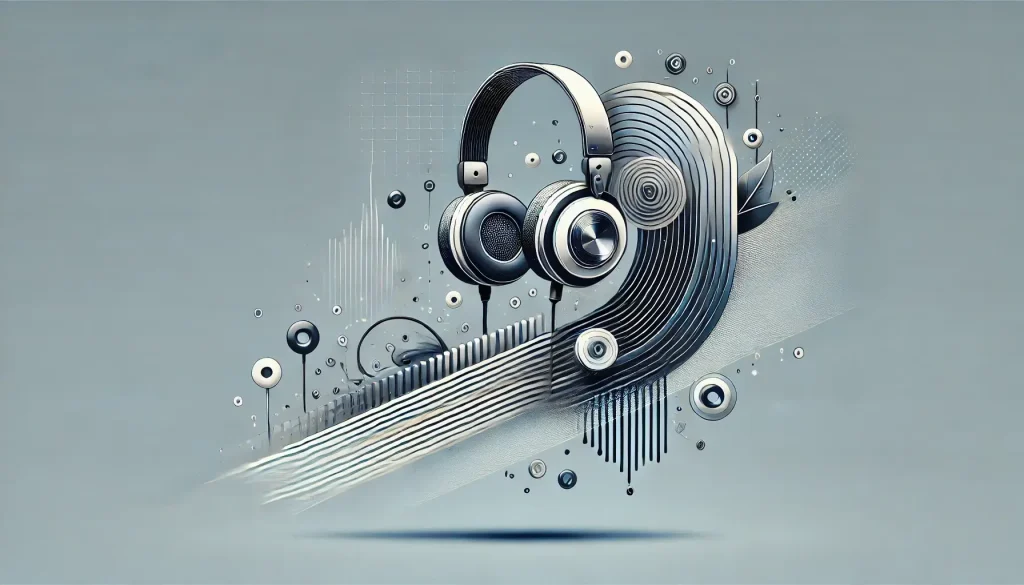
2週間の徹底検証を経て、Kiwi Ears 「Altruva」がどのようなヘッドホンなのか、その全てが見えました。
最後に、この記事の総まとめとして、購入を検討しているあなたの背中を押す、あるいは引き留めるための「最終ガイド」をお送りします。
メリット(明確に優れている点)
- 圧倒的な音場の広さと空気感: 1万円台で体験できるとは信じがたい、前後左右上下に広がる立体的な音場。
- 透明感と抜けの良さ: 刺さらずにどこまでも伸びる、美しい高音域の余韻。
- 価格を超えたビルドクオリティ: 金属を多用した剛性の高いフレームと、シックなデザイン。
- 最高の装着感: 自己調整式バンドと、ベロアパッドの組み合わせは、長時間の使用でも疲れ知らず。
- 豪華な付属品: 音質と装着感を選べる「2種類のイヤーパッド」が標準で付属する。
- 「育てる」楽しみ: アンプの性能向上に、素直すぎるほど応えてくれるポテンシャルの高さ。
デメリット(購入前に知るべき注意点)
- アンプが「ほぼ必須」であること: スマホ直挿しでは真価の1割も発揮できません。このヘッドホンの性能を引き出すためには、最低でも1万円クラスのドングルDAC、理想は据え置きアンプの導入が「前提」となります。
- 盛大な音漏れと、皆無な遮音性: 公共の場所での使用は絶対に不可能です。「静かな自室」専用機です。
- 低音の「量」は少ない: 重低音のズンズンとした「圧」や「迫力」を求める人には全く向きません。
「Altruva」の真価を引き出す「最低ライン」の環境は?
「据え置きアンプが理想なのは分かった。でも、最低限、どれくらいの投資が必要か?」 という疑問にお答えします。
- 最低ライン(必須): 1万円前後の「ドングルDAC」
- (例:iBasso DC04PRO, FiiO KA13, Shanling UA4など)
- これでようやく「1万円のヘッドホン」としてのスタートラインに立てます。
- 推奨ライン(理想): 2万円前後の「据え置きDACアンプ」
- (例:FiiO K7, Topping DX3 Pro+など)
- Altruvaの持つ「音場の広さ」「解像度」を100%引き出し、5万円クラスのヘッドホンと戦える音質を手に入れるための投資です。
「Altruva」が「最高の選択」となる人
- 初めて「開放型ヘッドホン」に挑戦してみたい人 (※ただし、同時にアンプも導入する覚悟がある人)
- 現在スマホ直挿しやドングルDAC環境で、将来的に「据え置きアンプ」の導入を考えている人
- 音楽の「迫力」よりも「空気感」「余韻」「解像度」を楽しみたい人
- ボーカル、アコースティック、ライブ音源を「生々しく」聴きたい人
- 長時間のデスクワークや音楽鑑賞で「疲れにくい」ヘッドホンを探している人
他のヘッドホンを検討すべき人
- ヘッドホンに「1円でも多くのお金」をかけたくない人 (※Altruvaは本体価格+アンプ代で、実質2万円〜の投資が必要です)
- 電車やカフェなど「家の外」でヘッドホンを使いたい人
- 同室に人がいる環境(家族など)で、音漏れを気にする必要がある人
- EDMやヒップホップの「重低音の迫力」を最優先する人
Kiwi Ears 「Altruva」レビューの総括
Kiwi Ears 「Altruva」は、非常に「不親切」で、同時に「最高にエキサイティングな」ヘッドホンです。
何の工夫もせずスマートフォンに挿すだけでは、その価値の1割も見せてくれません。
しかし、その声(98dBの感度)に耳を傾け、「君はもっとパワーが必要なんだね」と、適切な環境(アンプ)を与えてあげるだけで、1万円という価格の常識を遥かに超えた「広大な音場」と「生々しい空気感」という、極上の音楽体験で応えてくれます。
それはまるで、最初は懐かなかった猫が、時間をかけて世話をするうちに、ある日突然、喉を鳴らして甘えてくる瞬間に似ています。
単に「買って終わり」の消費的なプロダクトではなく、ユーザーの工夫と投資次第でどこまでも「化ける」可能性を秘めている。
Kiwi Ears 「Altruva」は、1万円台という価格で、オーディオ機器を「育てる」という、最も深く、最も楽しい趣味の世界へと誘ってくれる、最高の入門機です。
アンプという「鍵」を手にしたあなたを、「Altruva」はまだ誰も知らない音の世界へ連れて行ってくれるはずです。




